 |
||||||
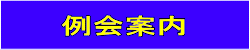 |
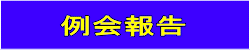 |
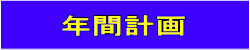 |
||||
|
||||||
|
|
||||||
| 閉 会 の ご 挨 拶 | ||||||
| 小田原市歩け歩けの会は、1965年に発足し、これまでに多くの皆様に支えられて 来ました。わが小田原城下町を中心に名所旧跡、風光明媚の環境に恵まれ、健康 増進と明るく楽しく元気な例会を推進し活動して参りましたが、諸般の事情により 今年度をもちまして閉会することになりました。 長きにわたり、神奈川県ウォ-キング協会並びに各加盟協会会員の皆様、地域公共 施設及び関係部門の皆様方、多くのご支援ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。 小田原市歩け歩けの会 会長 加藤 悦央 スタッフ一同 |
||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
| 小田原市歩け歩けの会 (神奈川県ウオーキング協会・加盟団体) TEL&FAX 0465-34-3265 電話は9~18時にお願いします |
||||||




